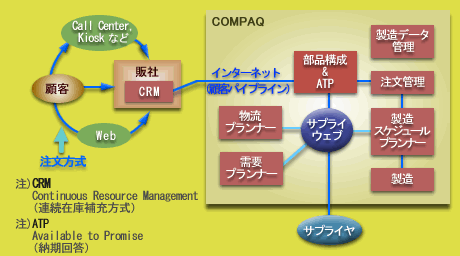
| 米国SCM視察報告-米国コンパック社 |
| 99年3月17日、米国コンパック社を訪問、SCM導入状況を視察させて頂きました。 事前に訪問の趣旨と主たる質問を伝えてあったため、説明頂いた担当ディレクターとマネージャーは、 こんなことを聞きに来た客は初めて、気合いを入れてプレゼンを作って来た、ということで、 盛りだくさんの内容となっていました。実際のSCM推進者という立場から、 システム以外の業務に関する質問やシステム選定理由、デルのSCMとの違いなど、 広範囲にわたった質問に分かり易く回答して頂きました。以下、その報告と感想です。 | |
| SCMへの取り組み | |
| 米国コンパック社は、最大手のパソコンメーカー。SCMへの取り組みは、 95年からメキシコにて試行、96年から製造で本番開始、98年には全製造部門に拡張、現在57の販社、 8の製造工場で利用している。 | |
| 新システムの目的 | |
| 米国コンパック社の販売方法は、ディーラーや販売店を通す間接販売。
このため、ある程度の完成品在庫、流通在庫は発生することになる。
新システム構築の狙いは、これまでの見込生産方式を継続しつつ、販売チャネルを対象とした 受注生産や受注仕様生産といった方式に対応できるSCMを実現することにある。 米国コンパック社のSCMは、次の3つの基本的な考え方に基づいている。 |
| 1 | Beyond the inside virtual "four walls" → 社内の4つの管理の壁(営業、製造、調達、会計)を超える | |
| 2 | Linking customer's customer to supplier's supplier → 販社から最終顧客、サプライヤから2次サプライヤ以降までをリンクする | |
| 3 | 協業の推進と情報の共有によってデシジョンメーキングを向上(迅速、正確)させ、 かつコストとリスクをパートナーシップで共有する |
| その情報システムへの主要な要件は以下のとおり: |
| 1 | 注文の95%の納期が確約できること(高い製造能力の達成、またはATP分析精度向上) | |
| 2 | デリバリーサイクル時間は5日 | |
| 3 | 在庫回転率の向上 |
| 新システムの概要 | |
| 新情報システムは、実行系と計画系と大きく2つに分けられる。
実行系業務は、ERPソフトであるSAP社の「R/3」を利用、できるだけカスタマイズせず、 業務とデータの標準化を行っている。このため、既存の仕事の流れをリエンジニアリングする必要が出てくる。 従来の「仕事に合わせて情報システムを作る」というアプローチからERPソフトに合わせて業務を改善するという パラダイムシフトが起きた。 リエンジニアリングによって中間レベルの管理職がコントロールを失う傾向にあることが分かったが、 リエンジニアリングは会社の方針として、パイロットシステムを構築し、成果を確認しながら段階的に導入する ことで解決していった。 実行系の「R/3」は、すべてのシステムの中核に位置付けられ、コストに関する流れをすべて管理している。 一方、計画系のシステムは、需要予測、製造計画などは自社開発、人事管理にはPeopleSoft、 資材需要シミュレーションにはManugisticsなどを利用しているが、計画に関るソフトはi2T社の「Rhythm」 に置き換えて行く方針とのこと。データーベース統合なども「R/3」にインタフェースを合わせて行く計画 とのことである。 これまで週次だった生産計画を、新システムでは日次レベルでできるようにした。 これによって発生する対外的なリエンジニアリングについては、サプライヤー自身のシステム変更が必要な 場合もあったが、メリットを説明することで納得してもらった。納得してもらえなかった場合は別の サプライヤーに変更した。 これによって生産計画の細かな変更に対応して、部品調達量が柔軟に変更できるようになり、 過剰な部品在庫を抱えることは少なくなった。 |
| 情報の流れ | |
顧客(販社)、サプライヤーとの情報の流れと情報システムの関連を下図に示す。
ここではインターネットを利用した顧客、サプライヤーごとのウェブがあり、注文、販売予測、
製造予測などのデータがやりとりされる仕組みが描かれている。
EDIは順次ウェブに移行していくそうである。
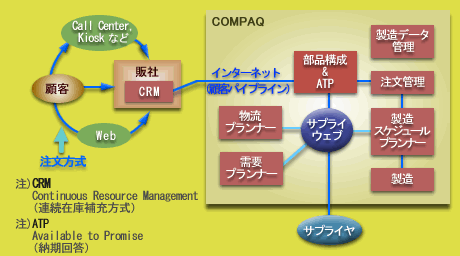
|
| 感想 | |
| ERPの「R/3」を中核システムに、そこにSCMソフト「Rhythm」でSCMシステムを構築し、
システムに合わせて業務をリエンジニアリングしていく、という発想は日本の製造業にはない。
システム部門が主導権をもつこと、経営がそれを理解すること、などは日本での実現は難しそうだ。
システムは1社と心中せず、いろいろなパッケージを要件ごとに選択していくこと、システム間の
インタフェースは自社で標準化定義して開発していくことなど、よほどシステム部門に力がないと
実現できないことばかりだ。
業務リエンジニアリング、SCM、インターネットとシステムとは、密接にかかわっており、 その推進者としてシステム部門が大きな主導権を持たねばならないことを実感した。 |